MENU

社会保険の事務
社会保険(健康保険・厚生年金)制度は国が保険者となり企業の福利厚生設備の基本的な制度で、特に中・小企業に働く労働者の健康福祉の大切な制度です。
法人企業は、社長お一人でも社会保険に加入しなくてはなりません。また、社会保険の手続きは年金事務所や健保協会並びに健康保険組合に対して多岐にわたる届出や申請・請求があります。
従業員の採用や退職に伴う被保険者の資格取得届・資格喪失届けの手続きや給与の固定的賃金の変動に伴う保険料の変更届(月額変更届)、また従業員が病気になり入院等のため会社を休んだときの傷病手当金や本人や配偶者が出産した場合の出産手当金・出産一時金の給付関係の請求事務があります。
毎年7月には社会保険料の標準報酬月額算定基礎届の手続き事務があります。
これらの手続きは所轄のけんぽ協会・年金事務所・健康保険組合で行ないます。
弊所ではこれら社会保険の手続書類を御社に代わって作成し手続きを代行いたします。

労働保険の事務
労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は従業員を一人でも雇用した場合、必ず加入しなければならない強制保険制度です。
労働者災害補償保険(労災保険)は、従業員の勤務時間中(業務上)の傷病や通勤途上で怪我をされた場合に、保険給付されるもので、治療のための療養(補償)給付、休業を余儀なくされたときの休業(補償)給付、治癒したが障害が残った場合の障害(補償)給付などがあります。これらの手続きは、労働基準監督署で行ないます。
雇用保険は、従業員が退職した場合に雇用保険(失業保険)の給付を受けられるようにします。
また、60歳に達し在職労働者の高年齢雇用継続給付金や介護や出産のため一時会社を休んだ場合の休業給付金もあります。これらの手続きは、公共職業安定所で行ないます。
幣所ではこれら労災保険・雇用保険の手続書類を御社に代わって作成し、労働基準監督署や公共職業安所への提出を代行いたします。

給与計算の事務
給与計算はどこの会社でも必ず行なわれている大変重要な事務の一つです。
しかしながら、法律的な専門知識を要する必要があり、その事務作業には、かなり多くの時間と労力を要しています。
給与は、労働基準法の第24条で
- 通貨払い(現金で支払いなさい)
- 直接払い(直接労働者本人に渡しなさい)
- 全額払い(賃金の全額を支払いなさい)
- 毎月1回以上払い(毎月1回以上の回数で支払いなさい)
- 一定期日払い(一定の日を特定して支払いなさい)
の5つの原則が定められています。
毎月の給与計算によって、そのデータから社会保険料の月額算定届けや算定基礎届け・労働保険の概算確定保険料の年度更新・所得税の年末調整のなどをリンクさせ従業員の雇用管理をトータルに事務処理します。
給与計算は、コンピューターで処理いたします。給与計算事務に関わる関係書類は、必要に応じプリントアウトする事が可能です。
幣所では御社に代わって給与計算に関わる一切の事務を代行いたします。
∗ただし税理士法に係わる事項については、御社顧問税理士様のご承諾を必要とする場合もございます。
就業規則の新規作成・見直しは
「社会保険労務士松山事務所」へ
ご相談ください
就業規則は会社の基本的決まりごと・会社の憲法です。労使双方の理解と遵守がより良い関係の基本。
正社員・アルバイト・パート等の職種を問わず。10人以上雇用したら必ず作成・届出が必要です。
就業規則に関するお問い合わせは
受付時間:平日10:00~17:00土・日・祝日はお休みです
メールでのお問い合わせは下記ボタンの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。
初回1時間 無料!
就業規則に関するご相談は電話・ZOOM・来所相談いずれにても対応いたします。お気軽にご相談ください。
- 初回1時間は無料です。1時間を超えた場合は30分ごとに5500円(税込)の有料となります。
- 30分未満の延長であっても5500円(税込み)の相談料が発生します。
御社の就業規則は法律に沿って整備されていますか?
トラブルが発生する前に就業規則の整備を行いませんか?
就業規則は法律の改正があった場合は必ず修正しなければなりません。 また就業形態が変わったなど、社内の勤務体制に変化があったときなど、 必要に応じ就業規則の変更が必要になります。 今、御社の就業規則の始業・終業について1日8時間、1週48時間 の労働になったままではありませんか。
■労働者が10人未満でも作成しましょう。
就業規則は労使トラブルの際、会社を守る重要なアイテムです。
従業員が10人未満の事業所では労働基準法では就業規則を作成義務はあり
ませんが、労働者がいれば、そこには労使トラブルが発生する可能性は十分にあります。就業規則を作成しておくことによって残業、退職、懲戒などのトラブルにな
りやすい場面で、解決策への有利な事情を主張することができます。
■ 古い就業規則は定期的に見直しをしましょう。
貴社の就業規則は作りっぱなしになっていませんか?
労働基準法等労働関係法令は幾度となく改正されています。
法律の改正により重要な部分が改正されたり、会社の労働形態が変更されたりした場合、就業規則の見直しも必要となります。
常に法律と対峙した就業規則に修正しなければなりません。
就業規則に必要な記載事項?
絶対的必要記載事項
就業規則を作成するにあたって、労働基準法上必ず記載しなければならない事項が定められています。
これを 絶対的必要記載事項 といいます。
| 労働時間に関する絶対的記載事項 |
|
|---|
就業規則には、仕事の始まりの時間(始業時間)と終りの時間(終業時間)や休憩時間などの労働者の一日の労働時間に関する事項、労働者の所定休日 年次有給休暇・産前産後休暇・育児介護休暇 特別有給休暇などの休暇に関する事項、また、シフトや交代勤務が存在する場合はこれらの就業時転換に関する事項は必ず記載しなければなりません
| 賃金に関する絶対的記載事項 |
|
|---|
賃金に関する事項は、労働者にとって極めて高い関心事であり、基本的生活基盤の根源をなすものです。
就業規則には賃金の決定、計算方法、締切日、支払日、昇給に関する事項を
必ず記載しなければなりません。
| 退職に関する絶対的記載事項 |
|
|---|
中途退職や定年退職等の退職に関する事項のほか、解雇に関する事項についても、その根拠となる懲戒事項の記載や手続等についても記載が必要です。 また、定年年齢を65歳未満に定めている就業規則は高年齢者雇用安定法により定年を65歳にするか、定年制を廃止するか、65歳までの継続雇用制度の導入をするなどの変更が必要になります。
相対的記載事項
相対的記載事項は、絶対的必要記載事項の他、会社のルールとして
すでに実施されている事項について就業規則に記載しなければなりません。
| 具体的には |
|
|---|
その他全従業員に適用される可能性のある旅費交通費や休職規定については 相対的記載事項として就業規則に記載しておきましょう。
任意的記載事項
任意的記載事項は、法的規制はなく会社の判断で自由に掲載することができます。
例えば、就業規則等の制定、改定等の履歴や会社の社訓、経営方針など
企業文化等一般的なもので、雇用関係に影響する労働条件や就業方法は
相対的記載事項に記載する事項となります。
事業所毎に就業規則の作成・届出義務があります
就業規則は企業単位ではなく事業所(場)単位で作成届出ることが必要です。
本社(本店)以外に支店、営業所、工場、出張所、作業所等名称の如何に
かかわらず事業所を設置している場合、 その事業場に従業員が10名以上のいる事業所は就業規則を作成し、
事業所所在地の所轄労働基準監督長に届け出なければなりません。
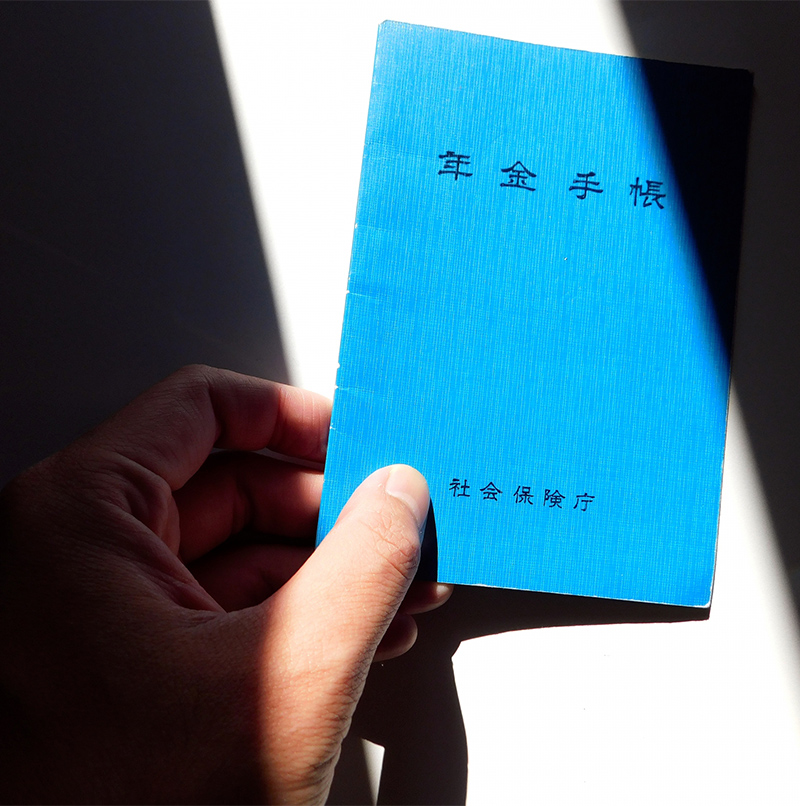
年金裁定請求業務
老齢年金の請求はお任せください
年金の裁定請求は親身になってお手伝いさせていただきます
年金は受給権が発生しても待っていては貰えません。
年金は60歳に到達したならば老齢厚生年金の裁定請求をして老後の安定した収入源を確保しましょう。
老齢厚生年金は60歳にならないと支給されません。昭和16年4月2日以降生まれの者については生年月日により厚生年金の定額部分(65歳以降は老齢基礎年金に姿が変わります)が支給停止となっており、60歳からの支給は報酬比例部分のみの支給となっています。
又、年金には老後の年金のみならず被保険期間中に障害に遭われ時には障害年金・被保険者が死亡したときは遺族年金等を受給する事が出来ます。
私どもでは年金受給資格者に代わってこれらの裁定請求書を作成し、年金事務所への届け出に係わる一切の業務を代行いたします。
